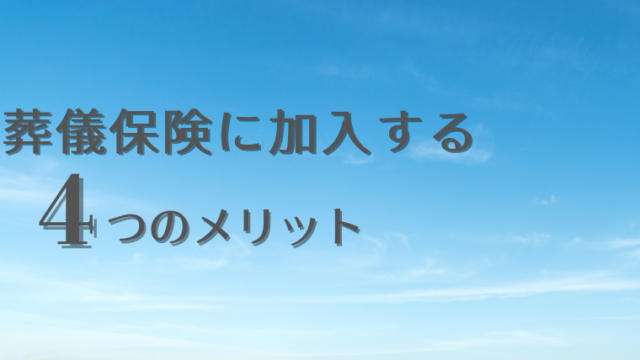最近、血圧が高いの。。医療保険には入っているんだけど「持病があっても加入できる医療保険」にも入った方が安心かしら?月額5,000円で入れるらしいの。
その5,000円、健康寿命を延ばすことに使う方がいいと思います。
えっ!医療保険は不要ってこと?
医療保険が不要な理由を説明します!
Contents
老後に医療保険を手厚くする必要はない2つの理由

老後に医療保険を手厚くする必要はない理由は以下の2つです。
- 高額療養費制度がある
- 在宅医療が充実してきた
①高額療養費制度がある
高額療養費制度とは同一月に高額な医療費の自己負担が必要となった際に、限度額を超えた分について払い戻しを受けられる制度です。
ただし保険適用外の医療費及び入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは高額療養費の支給対象にはなりません。
高額療養費の算定における自己負担限度額は当該年度(4月から7月までの診療費については前年度)における住民税の課税状況および所得に応じて下記のように決定します。
自己負担限度額について(8月~翌年7月)
自己負担限度額は、年齢や所得に応じて定められています。
| 適用区分 | 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※ |
| ア |
基礎控除後の所得が |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ |
基礎控除後の所得が |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ |
基礎控除後の所得が |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ |
基礎控除後の所得が |
57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12ヶ月以内に限度額を超えた支払いが4回以上あった場合の4回目以降の限度額
| 所得区分 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B |
| 現役並み所得者 3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100円※1] |
|
| 現役並み所得者 2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円※1] |
|
| 現役並み所得者 1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円※1] |
|
| 一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円※2 | 57,600円 [44,400円※3] |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月以内に限度額を超えた支払いが4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※2 8月~翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計の限度額)は144,000円
※3 過去12か月以内にBの限度額を超えた支払いが4回以上あった場合の4回目以降の限度額
入院・手術などで1か月の医療費の自己負担額が高額になることがあらかじめ分かっている等の場合、「限度額適用認定証」(※)(申請により交付)を医療機関等の窓口で提示すると医療機関での支払いを限度額までにすることができます。
なお70歳以上の「一般」及び「現役並み所得者3」の方については、高齢受給者証を医療機関に提示していただくことで限度額までの支払いとなりますので、限度額適用認定証は不要です。
※住民税非課税世帯・低所得者1・2の人は、「限度額適用認定証」に食事代(標準負担額)が減額される「標準負担額減額認定証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付
②在宅医療が充実してきた
最近では在宅医療が充実してきました。入院ありきの医療保険では給付金を受けとれるとは限りません。
自宅や高齢者向けの施設などに医師や看護師などが訪問して、診察や治療、健康管理などを行うこと。対象となるのは、医療機関への通院が困難となった患者。
超高齢化社会を目前に控えた日本では、第3の医療として在宅医療は増加すると言われています。
厚生労働省が定義する在宅医療で受けられる主な6つのサービス
| 訪問診療サービス |
| 医師が訪問し、診療を行います。 |
| 訪問歯科診療・訪問歯科衛生指導 |
| 歯科医師・歯科衛生士が訪問し、歯の治療や入れ歯の調整等を通じて食事を噛んで飲み込めるよう支援を行います。 |
| 訪問看護(医師の指示のもとで実施) |
| 看護師等が訪問し、安心感のある生活を営めるよう処置や療養中の世話等を行います。 |
| 訪問薬剤管理(医師の指示のもとで実施) |
| 薬剤師が訪問し、薬の飲み方や飲み合わせ等の確認・管理・説明等を行います。 |
| 訪問によるリハビリテーション(医師の指示のもとで実施) |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問し、運動機能や日常生活で必要な動作を行えるように、訓練や家屋の適切な改造の指導等を行います。 |
| 訪問栄養食事指導(医師の指示のもとで実施) |
| 管理栄養士が訪問し、病状や食事の状況、栄養状態や生活の習慣に適した食事等の栄養管理の指導を行います。 |
在宅医療を受ける際は、各種健康保険が適用されます。
最大3割負担の費用で治療やサポートを受けることが可能です。
なぜ、老後に医療保険を手厚くしたくなるのか?

老後に医療保険を手厚くしたくなる理由は、主に以下の3つです。
- 高齢になると病気リスクが高くなる
- 高齢になると入院が長期化する
- 人生100年時代に備える
そうそう!「2時間サスペンス」の再放送を見ていると、こんなCMばかり流れてくるのよ・・・
「家族に負担をかけない」とか「ガンの入院手術にかかる費用をご存知ですか?」とかね。
2021年に金融庁は「保険会社向けの総合的な監督指針」を公表しています。
(以下、抜粋)
保険会社や保険募集人等が保険募集を行う際には、顧客の意向を把握し、意向に沿った保険契約の提案を行うことが重要です。
今般、この点について、公的保険を補完する民間保険の趣旨に鑑み、保険募集人等が公的保険制度について適切に理解をし、そのうえで、顧客に対して、公的保険制度等に関する適切な情報提供を行うことによって、顧客が自らの抱えるリスクやそれに応じた保障の必要性を理解したうえでその意向に沿って保険契約の締結がなされることが図られているかという点などを監督上の着眼点として明確化するものです。
金融庁は「公的保険制度の情報提供をしたうえで、保険の勧誘をしてくださいね!」って、保険会社に言ってます。
このような通達を出すということは、適切な募集活動が行われていないケースがあるということです。営業職員の説明を鵜吞みにするのではなく、自身で保険加入の判断しなくてはなりません。
公的保険制度をしっかり理解したうえで、民間の医療保険が本当に必要かどうかを検討することが重要です。
老後の過度な心配も医療保険も必要ない!【医療予備費を預貯金で蓄える】

ある程度の年齢になり、老後が具体的になってくると自身の健康に不安を感じるでしょう。まして同世代の友人や知人が入院すると、不安は増しますよね。
幸い日本の「国民皆保険制度」には、充実した高額療養費制度があります。
医療費の負担が増えることを、過度に心配する必要はありません。
ただし公的医療保険の対象となるのは、治療費・薬代・入院費用だけです。入院中の食事代や差額ベッド代・入院や通院にかかる交通費などの費用は自己負担になります。
公的医療保険で補えない費用は必要ですが新たに医療保険に加入し、その保険料が家計を圧迫するようなことになれば本末転倒です。
「医療予備費」を蓄えておき、本当に必要なときに使うほうが合理的だとは思いませんか?